日本甲虫学会 調査観察例会2023・24
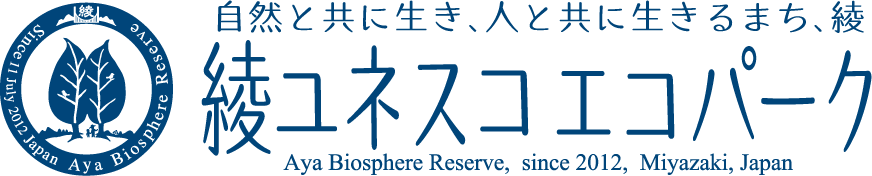
「(仮題)宮崎県綾ユネスコエコパーク調査観察例会2023・24報告」の発刊に向けた方針」について
文責:初宿成彦
連絡先:hippodamia13@gmail.com
【発刊形態】
・2023年・24年の調査観察例会の成果を「地域甲虫自然史」第8号として、2025年度に出版する(2024年度日本甲虫学会総会にて承認済)。
出版日(目標):2025年10月31日
出版形態:
①PDF:出版時に即時ネット公開
②希望者には紙印刷販売:オンデマンド印刷、定価未定(赤字にならない程度に)
【地理的範囲】
綾ユネスコパーク内とする(綾町全部+周辺市町村の一部)
| 国土地理院 | 等高線が細かい | |
| グーグル | 景観写真などを貼り付けている | |
提出方法:できればデータ提出用シート(
提出データ内容:調査観察例会の記録であるということを念頭に、調査観察会当日の未発表データを中心にリストをお願いします。普通種など既記録種も含めます。既にいただいている方もありますが、2025年分や古い採集品など追加データも歓迎します。エコパークエリア内の未発表データならOKとします。
引用:甲虫学会宮崎綾調査観察例会当日で得られた知見を、既に原著論文や短報で発表されている(予定も含む)場合は、引用しますから、お知らせ願います。
〆切:9月10日。できるだけデータを盛り込みたいので、〆切日については応談ですから、遅れる方は早めにお知らせくださいませ。
標本の所蔵先:宮崎県立博物館を推奨します(普通種でも同定ラベルを付してください)。私の経験上も、個人所有よりは地元の博物館で保管いただいたほうがいいです(特に普通種)。今回掲載されない未同定標本も含めていいと思います。地元に託しておけば、将来的に明らかになったり役に立ったり、すると思いますので。倉敷大会の初日(11月15日:土)の総会に初宿は顔を出すつもりでいますので、宮崎県博への提供分の標本は持参いただいたら倉敷で受け取るようにします(2日目は不在です)。郵送の場合は初宿または宮崎県の笹岡康則さん・木野田毅さんへご相談ください。
標本写真:これぞという種(あるいは特に同定が疑念をもたれそうなもの)は標本写真があるといいと思いますので、可能な方はお願いします。
同定についてお願い:学会諸氏の専門分野において、ご協力をお願いします。
調査地各論(下記の書き込み入り地図を参照)
文責:木野田毅(2023年3月)
※2025年夏まではデータ追加可です。
① 綾南川沿い(てるは大吊橋から川中自然公園)方面、県道26号を西に向かいます。全線舗装路です。川中自然公園のトロッコ道に接する山地は、コアエリアです。湿度が高く、ケシキスイ、ホソカタムシ、オオキノコムシなど、朽木くずしやスプレーイングに向いています。県道では灯火採集の良いポイントもあります。
② 大森岳林道(竹野集落から大森岳林道に入ります。400mでゲートがあり、施錠を開錠する必要があります。入林届けを全員分出しますので、鍵番号はお知らせします。)舗装路でほとんどのコアエリアを通過できますが6km過ぎから砂利道となります。雨天後は全路線で落石をどかしながらの走行が必要です。綾北川を見下ろす場所での灯火採集や尾根から下る場所での林内の採集ができますが、上下の移動があるので体力が要ります。コアエリア内は川中自然公園と同様に巨木があります。照葉樹林内はどこも暗い感じがしますし、樹高30mものカシ類の葉をスイープするのは大変です。
③ 綾北川沿いの県道360号も湿度が高く、舗装路での採集、道路沿いの樹林に入っての採集が魅力です。ゲートを解錠して入ります。常時通行止めですので。林道とは別の鍵番号が要ります。お知らせします。
④ 茶臼岳林道から式部岳へのアプローチ。茶臼岳林道沿いの採集やすぐ横の深年川沿いの樹林が魅力です。林道を歩いての採集だけでも楽しい場所です。ゲートからすぐ、法面にウツギが多い場所がしばらく続きます。8kmもの長い林道です。最終地点から式部岳の登山道を歩くと沢沿いにサワグルミが出てきます。沢ではサワダマメゲンゴロウも確認しています。ブナ帯を源流とする水質最高の川です。
式部岳に登ってブナ帯を調査する方も、この林道を進みます。最後の1kmほどが、荒れることがあり、できれば四駆の車が心強いです。
⑤ 馬事公苑には、馬舎があり、馬糞にくる甲虫が期待できます。また、この馬事公苑のすぐ近くの綾神社から街中セラピーコースになっている照葉樹林のこぢんまりした谷があり、小学生でも散策する安全な林内での採集が可能です。
甲虫学会ページトップへ